皆さんこんにちは!
今回は、一級建築士学科の勉強手順について解説していきたいと思います。

このブログは
・4年制大学建築学科卒
・社会歴5年目
・転職歴2回
・取得資格
一級建築士、宅建士、賃貸不動産管理士(合格のみ)
の経験を元に書いております

今回のゲストはYさん!
今年一級建築士を取得するべく、勉強を始めたんだよね?
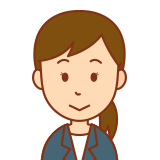
よろしくお願いします!
正直、5科目もあるので何から取り組むべきなのか、、、、
順番で行くと計画、環境、法規、構造、施工ですがその順番でいいでしょうか。

ふむふむ、、、
やっぱりどこから取り組むべきなのかは難しいよね!
一緒に紐解いておこう。
一級建築士の学科について

みんなわかって入ると思うけど、一級建築士の学科試験の内容から説明していくよ!
一級建築士の学科試験は、建築に関する幅広い知識を問う重要な試験です。試験は5つの科目に分かれており、合計125問の四肢択一式のマークシート方式で実施されます。
試験科目と出題数について
- 学科Ⅰ 計画 20問
- 学科Ⅱ 環境・設備 20問
- 学科Ⅲ 法規 30問
- 学科Ⅳ 構造 30問
- 学科Ⅴ 施工 25問
試験時間 (⚠5科目別々ではなく3区分に分かれている)
- 学科Ⅰ・Ⅱ:2時間
- 学科Ⅲ:1時間45分
- 学科Ⅳ・Ⅴ:2時間45分
合格基準(その年によってブレるがだいたいの想定)
- 総得点が90点程度(最高97点、最低87点)
- 各科目の足切り点をクリアする(基本各科目で過半数以上の得点)
留意事項
- 学科IIIの試験時のみ、法令集の持ち込みが可能。
- 学科試験に合格すると、その年を含めて5年以内に実施される設計製図試験のうち、3回を任意に選択して学科免除で受験が可能。

合格点に幅があるね。
ただ97点は異常な年のため、基本的には90点前後だよ!
あとは足切りだけ注意だね。
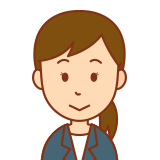
それでも72%か、、、
やっぱりかなり取るのが難しく感じますね。

確かに甘くはない道だけど、科目ごとの特徴を知れば怖くないよ!
次は優先教科について見てみよう!
科目ごとの優先度と特徴について

科目には問題数以外にも特徴があるよ!
その特徴を認識することで合格点に近づけやすいので対策するためにもしっかりと頭に入れていこう!
優先度第一位 法規
法規書を持ち込めることもあって点数が安定しやすく、配点も30点と高いためどのサイトを見ても最優先で書かれているのではないでしょうか。
では注意点についてです。
時間が足りないため、法規書で一問ずつ丁寧に引いていてはいけない。
法規はそれこそ時間との勝負になります。
答えは手元にあるが時間内に引けるかが大きな鍵となりますので、どのあたりに何があるかはもちろん把握すること。
迷っていればタイムオーバーも全然あります。
勉強方法としては教科書の把握が終わったら、30問で時間を計ってやることをおすすめします。
また、法規が早い人から聞いた意見ではよく出る内容は暗記していると聞きました。
参考にやってみるのも手ですね。
目標点数は 26点以上です。

5科目あるけれど、法規だけは確実に取れるようにしよう。
他の教科で取り返すのと法規で点を取るのでは安定性がぜんぜん違うよ!
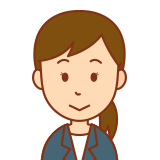
法規は、持ち込み可なので勉強時間はあまりいらないと思っていました、、、時間内に終わらせられるように、反復して30問を時間計測して行います!
優先度第二位 構造
正直、施工と優先度に差はありませんが早めに理解しておくことが重要な科目ということで構造を優先度二位としました。
計算問題は慣れるまで解く(←こっちが暗記)。構造知識については理解できるように調べる。
よく計算へのアレルギーから敬遠する方が多いのですが、暗記で十分対応な問題ばかりです。過去問を何度も解いて感覚を掴んでください。
また構造知識を問われる問題で聞き慣れない単語や状況が理解できない場合、調べるorわかる方に聞きましょう。言葉だけ見ていても頭に入ってきません。
過去問からの出題が多く、目新しく感じても理解していれば解ける問題となっています。
乗り越えるハードルは高いですが、乗り越えれば安定しやすく心強い武器となります。
目標点数は 23点以上です。

一級建築士の学科試験においてもっとも理解を要する科目だね!
構造でも高得点を取れれば、あとの3科目は足切りを回避するだけだよ。
得意科目にできれば学科合格はグッと近づくね!
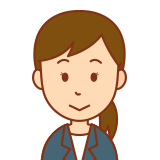
どうしても計算があるし、苦手意識が高いけど頑張りどころですね、、、、
優先順位第三位 施工
続いては、施工ですね。点数順か?といわれそうですがそうではありません。
施工基準・工事方法・材料の性質はそう変わるものではなく、新傾向がでにくい。
覚えた分だけ点数は上がると言えます。
ひたすら暗記といった教科になりますが、構造同様に理解しづらい・頭に入らない場合はどの部分について覚えているのか調べて写真等を見ることで理解しましょう。覚えやすいと思います。
目標点数は 19点以上です。

本当に覚えた分だけ取れるといった科目だね。構造がどうしても理解できない、、、そんなあなたは脳筋で施工を暗記も悪くないね!
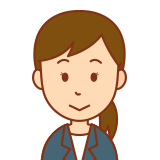
暗記のほうが得意なので、構造で取れない分を施工でカバーのほうが向いてるかも!
優先順位第4位 環境・設備
ここからは厄介な科目となってきます。
正直、足をきらなければ問題なし。
建築業界全体が省エネ化傾向にあり、それに伴う施策・新設備もあるため新傾向問題がだしやすい。
ただ、省エネ化が進んでかなり問題傾向が落ち着いてきたこともあり、過去問と各社が出すテキストを押さえていれば足切りをくらうことはないと思います。
教科書の内容を把握し、問題集を解けるようにすれば問題ないです。得意教科には設定しないようにしましょう。
目標点数は 13点以上です。

内容が好きだからといって得意科目にはしないようにしよう!
環境・設備で他の科目を補うことを考えるのは不安だね。
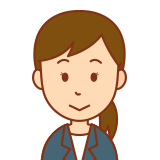
過去問で解けても、新傾向問題が出てしまえば正答が難しくなりますね。
その年のトレンドも押さえながら頑張ります。
優先順位第五位 計画
こちらも足をきらなければ問題なしといったところです。
基本問題を押さえ、建築実例は過去問中心にざっくりと理解する
正直、建築実例で新規がでれば得点は厳しいです。足切りしないためにも他の問題で落とさないよう基本を押さえましょう。
私はR3年の学科を受けて一発で通りましたが、計画は建築実例も内容も過去問だけでは正答肢に辿り着けない問題が多く、ここで足きられた受験者は数知れずといったところです。
計画取れたのは、運でしたね、、、勉強してれば取れた感じでもなかったです。
目標点数は 12点以上です。

一番時間をかけてほしくない教科かな、、、、
建築実例集は、ほかを勉強しづらいなにかの空き時間にやるくらいでいいと思うよ!
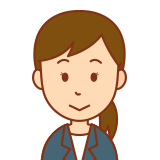
一番怖い教科ですが、対策も難しいとなれば時間をかけすぎないほうがいいということですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
もちろんすべての科目にしっかり力を入れられれば問題はありません。
ですが、時間が取れないのが社会人というものです。
点数につながりやすい科目とそうでない科目を理解し勉強に取り組めば、時間に余裕がない方でも合格できると思っています。
まずは、
- 法規は26点以上、安定して取れるようにすること(法規は取って当たり前)
- 構造・施工にて得意な科目をつくること(安心します。)
- 計画・環境設備はある程度やったらのめり込みすぎないこと(余裕がない限り優先すべきではない)
この3点と優先順位をみながら勉強にしていただければと思います。
次回は、学科は前哨戦!?熟練生をも振るい落とす地獄の製図試験についてでお会いしましょう!

合格目指して頑張ろう!
またね〜!
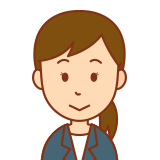
ありがとうございました!



コメント