皆さんこんにちは!
前回の一級建築士学科の勉強手順に続き、今回は一級建築士製図の勉強手順手順について解説していきたいと思います。

このブログは
・4年制大学建築学科卒
・社会歴5年目
・転職歴2回
・取得資格
一級建築士、宅建士、賃貸不動産管理士(合格のみ)
の経験を元に書いております

学科に引き続き、製図試験の勉強手順について解説していくよ!
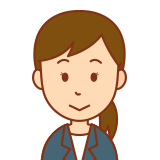
よろしくお願いします!
一級建築士の製図について
一級建築士の製図試験は、建築士としての実践的な設計能力を評価する重要な試験です。
試験概要
製図試験は学科試験合格後に受験する試験で、図面作成と計画の要点の記述が主な内容です。例年10月の第2日曜日に実施され、試験時間は6時間30分です。2025年度の試験は2025年10月12日(日曜日)に実施される予定です。
試験の内容について
設計製図試験の出題内容は以下のようなものです
- 課題文:試験問題に記載された設計条件や要求事項を含みます。
- 要求図書:以下の図面や資料の作成が求められます。
- 1階平面図兼配置図(縮尺1/200)
- 各階平面図(縮尺1/200)
- 断面図(縮尺1/200)
- 面積表
- 計画の要点等:建築計画、構造計画、設備計画、環境負荷低減等に関する7〜10問程度の質問に対し、文章で回答します。
試験時間は6時間30分で与えられた条件を正確に理解し、制限時間内に手書きで図面を作成・計画の要点を記述する必要があります。
採点と合格基準
採点は以下のポイントで行われます。
- 空間構成(建築物の配置・構造計画、ゾーニング・動線計画など)
- 建築計画(各住戸内の採光やプライバシーへの配慮、要求室の機能性など)
- 構造計画(耐震性を考慮した構造形式、基礎構造の計画など)
- 設備計画(給排水計画、給排気計画)
採点結果はランクI〜IVの4段階で評価され、ランクIが合格となります。

製図試験の時間は6時間半と長いけど、それでも時間が足りなくなる試験となっているよ。
- 求められる要件を満たし、計画するプランニング能力
- 正確かつ速く図面を作成する能力
- 計画した建物を文章で伝える能力
これらを学科で学んだ知識を使いクリアしていくわけだからかなりの労力と言えるね。
一級建築士製図試験の難しさについて
製図試験は合格する基準が年々高くなっていると言えます。
その理由としてあげられるのは下記の2つだと考えています。
- 大学卒業後すぐに試験を受けられるようになった。
- 各資格学校の質が上がっている。
以上の2点です。
大学卒業後すぐに試験を受けられるようになって変わった点
皆さんは、一級建築士を何年目で取りたいと思っていますか?
一年目?二年目?30代までに取れれば?
私の目標は社会人3年目でした。しかし、取得できたのは4年目です。
取れてよかったとも思っていますが、それと同時に二年目で製図を受けなかった自分に後悔した時もあります。過ぎたことなので考えないようにはしますが今でも思うことはあります。
仕事は、年が上がるにつれて忙しくなります。企業の中には、一年目は一級建築士の勉強に当ててもらえる企業もあるそうです。一年目といえば仕事でやれることは限られますので、、、、
いまから社会人になる方に押さえてもらいたいのは、一年目のアドバンテージを活かせ。
それ以外の人に言えるのは、今の生活のまま合格できると思うな。一年は試験のことだけ考えろということです。
大学卒業後、すぐに受けられるのは圧倒的アドバンテージ
各資格学校の質が上がっている点
以前に一級建築士・二級建築士取得を目指す方々への道しるべ③で資格学校について話しましたが、どこも合格に十分なサービスは提供できていると思います。
しかし、合格できる割合がある程度決まっているのがこの試験。試験元も落とすための罠をいくつも用意しますし受験生を迷わせてきます。
私が受けた年で言えば
- 2022年:指定階数をなくし、自由度をこの年から広げてきたように感じます。また、共用部を屋上にも設けることでセキュリティ面での動線が考えられるか。極めつけは、20m以深の支持地盤。
学科ではやっているものの基礎杭ではなく、地盤改良を書いてしまった方も何人かいるはずです。住宅では基礎杭なんてほぼ見ないため学科をなんとなく通したりした人には厳しい出題だったと感じます。 - 2023年:久々に登場した北側制限が印象的でした。さらには北に公園を配置する。もちろん北側斜線は日当たりを考慮するための斜線と理解していれば公園が緩和に入らないことはわかるでしょうが、ただ覚えている人にとっては道路斜線同様緩和があると考えてしまった人もいるのではないでしょうか。私は試験で見た際ゾッとしたのを覚えています。また、設備について要点記述で詳しく問われたことも印象的でした。おそらく一年目の方には対応しきれない部分だと思っています。
私が感じただけでも仕掛けがまだまだありますし、実際はそれよりも膨大にあるのだと思います。
これはひとえに受験者全員の質が上がってきているからと感じます。例年の解答例をみれば、ここ数年で問われる能力が格段に上がっていることがわかります。
私が受かった年で言えば、学科後スタートの講座で北側斜線は総合資格の課題ではやっていませんでした。日建学院は出たと聞いています。だから日建学院に入ろうというわけでもなく、資格学校もどこまで教えるか悩むほど試験の内容はレベルが上がっており対策が難しいということです。
一級建築士製図試験の取組み方について

説明した通りかなり難しい試験だということがわかったね。
学科試験に通った猛者達でも、3回製図に落ちる人もいるしそれ以上の人もいるときくね。
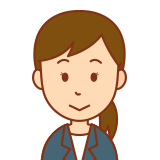
そんな、、、、こんな試験本当に合格できるの?

もちろん!
ここからは、合格するまでの体験を踏まえてこのブログを読んでくれた人が一人でも合格できるように説明していくよ!
一年目の立ち回りについて
一年目は特に時間がありません。学科を合格してから製図までの時間があまりにも短く、正直な事を言うと完成形になるには厳しいです。
しかし、採点においてはわざわざ図面をシャッフルすることは考えにくいため同じ一回目の受験者と採点されると言われております。
本当か嘘かはわかりません。ですが私の判断では本当だと思います。。
なぜか、、、、それは一年目と既受験者の図面のレベル差です。二年通った私だからわかることですが図面に込められる内容、精度が段違いに違うのです。もちろん既受験者レベルの方も現れますが、3クラスで各14人程度のクラスに1〜2人程度あとはこれで受かるのか?といった印象的でした。それでもクラスで5〜6人合格していたためです。
誰が見ても既受験者の方が、計画・環境・構造・設備の点でよく考えておりそれが図面化できている。
さらに言えば、要点記述も書き込まれているのです。
それでも一年目受験者が製図の合格割合(少し下回るか)程度通っているのということは、採点基準が初年度でまとめて採点するためゆるいと考えていいでしょう。
一年目で求められるものは、【諦めない心】が重要だと感じます。そのうえで順を追って立ち回りを説明させていただきます。
⚠一級建築士の大体の時間配分は、読み取り20分、エスキス(プランニング)1時間30分、1回目チェック30分、要点記述1時間、製図2時間40分、2回目(最終)チェック30分をベースに解説していきます。
作図手順を速くマスターする
まずは、製図時間は2時間45分以内を目指しましょう。早ければ早いほど良いのはもちろんです。
課題によって記載する量はもちろん変わるためぶれますが、どの課題でも2時間45分以内で書けることが合格への近道です。
前述で上げた中で時間を削れそうなものは製図かエスキスになりますが、エスキスはまとまらないときは本当にまとまりません。
そのうえで製図を限りなく早くしておくことは重要と言えます。

実際に、筆者は製図スピードがかなり遅かったよ!
はじめは3時間以内で計られても4時間ペース、、、、
字は書くのが遅い上に汚く、ペンを持つ手は震えているほどの不器用さ
それでも最後には2時間45分以内には書いていたね!
総合資格では、2時間30分で書けと言われていたけどほとんどの課題で書けませんでした。
ですがそれに近づくことはできる。これは不器用な私の心からのメッセージです。
いち早く書けるようになるには
- 各資格学校手順がありますが、見なくても書けるようになる。
- 階段やその年に重要となる部屋のレイアウトは、暗記する。
- 道具の持ち替えを減らす
この3点をまずおすすめします。
製図に入れば、機械的に手順通り書くこれが重要です。書き忘れも減りますし何より速いです。
試験問題に対するプランミスはエスキス時点で消しておき、残りの30分は問題用紙から書き忘れが無いかチェックする。
階段や部屋のレイアウトは特に書きなれていないと頭を使ってしまうところになりますので空き時間に部分練習をおすすめします。
また、2022年からボックスが禁止になり道具の持ち込みがかなり難しくなりました。机に直置になり、場所も狭い場合があるため道具が多ければ多いほど取りづらくなります。自分の中で精鋭の道具を選ぶことをおすすめします。(迷い猫のおすすめはこちら)
チェックのタイミング・方法を固める
各社おそらく読み取り時に線を引くと思いますが、その後2回のタイミングで必ずチェックをしてほしいのです。その二回のタイミングは
- エスキス終了時
- 作図終了時
かなりの人がこのチェックをおろそかにします。そんな簡単に見逃すわけ、、、、、と思いますか?
いいえ、人間はそこまで正確にできていません。
一回目のエスキス終了時は、作図前です。ここでは、問題用紙にチェックしながら建物の配置や要求室の確保等を確認します。
指定される位置と違う位置に配置したり、なぜか一室抜けたりしたまま作図に進めば取り返しのつかないことになってしまいます。
二回目のチェックは作図終了時。ここでは書き忘れですね。いつもは求められていないものが書くように指示があることも多いため、こちらも問題用紙に一つずつチェックをしながら確認します。
資格学校の統計でもこのチェック時間を長く取れた人ほど受かっているデータが出ています。

これは一年目以外にも言えることだけど、落ちているほとんどの受験生はランクⅢ・Ⅳなんだね。そしてここに位置する人たちの多いミスが国土交通省でも発表されており「要求室・施設等の特記事項の不適合」「法令への重大な不適合」だと書かれているよ。
◯防、◯特の書き忘れや延焼ライン忘れや要求室が足りないなど、、、
つまり、製図を速くしてチェック時間をしっかり設ければ防ぐことができる部分なんだ!
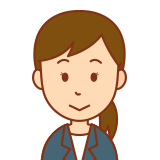
なるほど、製図試験は長いと思っていたけどチェック時間はいくらあっても足りない、、、目一杯頑張ることが重要なんですね!

筆者の場合は、製図が速くなかったため本番ではエスキスチェック終了時で2時間以内で切り上げていたよ!
エスキス見切りのスピードにおいては優れていたのかもしれないね。
プランにこだわり過ぎないことも大事だね。
二回目、三回目について(既受験者)
既受験者は、採点ポイントとされる、空間構成・建築計画・構造計画・設備計画についてより細かく見られます。これは一回目で話した通り、受験番号において部屋が分かれるためシャッフルしない限り既受験者で比べながらで採点されるからです。
そうなれば、書き込みや要点記述との整合性、構造や設備でおやっと思うところがあればかなり厳しく見られるのです。(又聞きになりますが、資格学校の先生が採点者から聞いたと教えてくれました。)
図面をきれいに書くことも大事かもしれませんね(遠い目)←筆者は壊滅的に字が汚い
実設計に近い整合性が問われるため、勉強にはなるので一回目落ちたからと言ってがっかりせずに二回目はより深い内容も理解できるよう頑張ることが重要です。
まとめ
いかかでしたでしょうか。
一回目でも二回目以降でも合格へ求められることは同じです。
法的重大な不適合や求められている特記事項に抜けがないかをしっかりチェックすることを徹底しましょう。その時間を確保するために製図とエスキスを、特に製図について洗練するのです。
そして、初年度は、初年度受験者と。多年度は、既受験者と採点されることを理解しそれに見合う図面を書けるように知識・図面を高めなければいけません。
そういった意味では資格学校へ通うことで他の生徒の図面を視察できることは良かった点だと思います。
まずは、皆さん製図時間とチェックマスターを目指して頑張りましょう!以上です!
次回!製図試験における三種の神器!?でお会いしましょう!

またね〜!
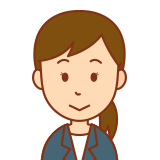
合格目指して一緒に頑張りましょう!



コメント