こんにちは!
今回は、宅地建物取引士の勉強第2回です。
前回に続き、今回は通謀・虚偽表示と詐欺について解説していきます。

このブログは
・4年制大学建築学科卒
・社会歴5年目
・転職歴2回
・取得資格
一級建築士、宅建士、賃貸不動産管理士(合格のみ)、管理業務主任者
(現在登録準備中)の経験を元に書いております。
用語説明
- 善意:ある事情についてしらない人
- 悪意:ある事情について知っている人
- 無過失:知らないことに関して過失がない。
- 有過失:知らないことに関して過失がある
- 無効:契約自体がなくなる(効力がはじめから無かったことになる)
- 取り消し:契約はあったが契約時点に遡って効力を消滅させる
- 第三者保護:第三者が善意(無過失も必要な場合あり)である場合、権利を主張できる
通謀・虚偽表示
通謀・虚偽表示とは、相手方と示し合わせて契約したと見せかけることですね。
それでは、今回も売買契約に例えて、登場者を意思表示者(表意者)のAさんと相手方のBさん、第三者のCさんでお見せします。
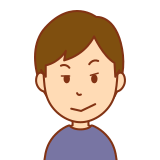
おれは借金取りに追われている、、、立派な土地が財産に残っているとバレてしまえば、差し押さえられてしまう。俺の大親友のBに協力してもらい、土地はBのものということにしよう。
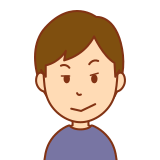
大親友のBよ!俺の土地を買ったことにして預かってくれないか。
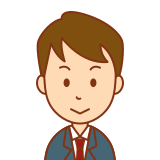
任せとけよ!親友だろ。
真意とは異なる意思表示のため、お互いの意思表示が合致していない状態です。
つまり、通謀・虚偽表示による契約は無効となります。

今回はAさん、Bさんに売買契約をする意思表示がないことからそもそも契約が成立していないということだね。
しかし、Bさんがこのまま土地を第三者へ売った場合、第三者が善意の場合にはAは無効を主張することができません。第三者の保護ですね。
事情を知らない第三者の権利を守るため、通謀・虚偽表示をしたAよりも第三者Cの権利を優先します。
通謀・虚偽表示まとめ
- 無効
- 第三者が善意であれば、Aは無効を主張できない
詐欺
詐欺については、皆さんもよく耳にする言葉のためわかりやすいのではないでしょうか。
詐欺により締結された契約は、騙されたものが後から取り消すことができます。つまり契約としては有効です。
これだけならかなり簡単なのですが第三者が出てきた場合に少し複雑になります。
それでは見ていきましょう。
詐欺を行ったBから売買契約によりCが取得した場合
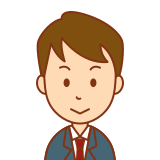
Aのやつちょろいし、Aの土地を騙して買って他のやつに売りつけて儲けよう。
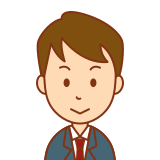
Aさん、この頃Aさんの土地のあたりはかなり金額が下がってきているんだ。いまなら私なら3000万円で買うよ!
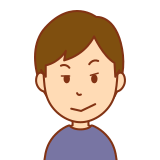
そうゆうことなら早く売ろう、、、契約します。
後日、、、、、
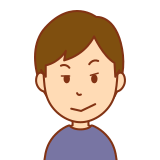
金が振り込まれてない、、、どうなってるんだ。
この間にBさんは何も知らない善意のCさんに売って、第三者保護でジ・エンド、、、、、、
とはならないわけですね。さすがに騙されたという落ち度はあれど、Aさんが可哀想。
そのため、心裡留保や通謀・虚偽表示とは違い、Cさんは善意であるだけでなく無過失であることが条件に追加されます。
そして、第三者がAを騙してBと契約する場合は、Bさんが善意無過失である必要があります。
詐欺まとめ
・契約は原則有効
・契約後取り消すことができる。
・BがAを騙して、Cへ転売した場合。Aは善意無過失のCに対しては取り消しを主張できない。
・CがAを騙して、AがBへ土地を売却した場合。Aは善意無過失のBに対しては取り消しを主張できない。

詐欺の場合は、騙されたAも可哀想ではあるため第三者等は善意に加えて無過失であることが追加されたね!
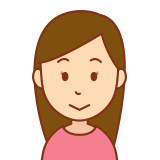
詐欺の場合はAも可哀想、、、、
確かに少し民法の考え方が理解できてきたかもしれません!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、通謀・虚偽表示と詐欺について説明させていただきました。
少し考え方のコツを理解し始めたのではないでしょうか?
次回は、強迫と錯誤でお会いしましょう!ありがとうございました!

またね〜!
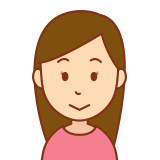
ありがとうございました!



コメント