| メリット | デメリット | |
| 分譲住宅 | ・一般の消費者を相手にするストレスがすくない ・棟数をこなせるため経験をたくさん得られる | ・当数が多いため業務的になりやすい ・予算に幅がないため同じ仕様になる ・お客様との接点はほとんどない |
| 注文住宅 | ・毎回お客様の要望は違うため飽きにくい ・分譲に比べ棟数が少ないため集中できる ・グレードの高い使用を支えたりする |
こんにちは!
今回は、建築学生の就職先について書かせていただきます。
建築学生・元建築学生で働いている方々!就職先(転職先)に悩んでいませんか?
そもそもどんな就職先があるのかよくわかっていない人も多いのではないでしょうか。
是非参考に読んでいただければと思います。

このブログは
・4年制大学建築学科卒
・社会歴5年目
・転職歴2回
・取得資格
一級建築士、宅建士、賃貸不動産管理士(合格のみ)
の経験を元に書いております。
私は何気なく建築学科に入り、特に将来を考えることもなく就活期に入りました。
一つ希望としてあったのは、大学まで出たのだから外仕事はやりたくない。
その程度の望みを持って就職活動を行いました。
最終的に決めた就職先はハウスメーカーで、注文住宅と分譲住宅を両方手掛ける会社でした。
当時、設計事務所のハードルを高く感じていたためハウスメーカーの設計を選んだことは必然だったのかもしれません。しかし、勉強のためと配属された施工監督の部署から移動できない社内状況を知り、1年で転職をしました。
その当時は施工監督としての経験もプラスだったので特に就職に失敗したなどとは思ってはいなかったのですが、次に入った会社、そして今の会社を経験したくさんの業種の方々と接することで学生当時の就職先についてかなり可能性を狭めていたなと認識しました。
このブログを読みに来てくださった皆様には選択肢が広がるような情報を提供しお役に立てれば
幸いです。
就職先について

今回のゲストは就活中の建築学生Kさんです。
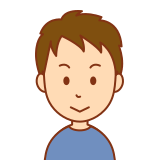
よろしくお願いします!
正直、就職先については設計課題の授業が苦手だったこともあり設計事務所はやめておこうかなと、、、
デザインを考えても褒められたことがなかったんです。
でも現場監督も大変そうですし、建築とは違う道もあるのかな〜と

(もったいない、、、)

学校の設計課題で設計に苦手意識をもつ人もいるよね!
でも実際の設計士の仕事はそれだけじゃないよ。
一緒に見てみよう!
設計事務所
設計事務所は図面の作成や申請関係*¹、監理*²を主に行う会社である。
私の学生時代のイメージでは、意匠系の研究室にいた学生ははじめに思い浮かべる
就職先ではないでしょうか。
やはり最初に思い浮かぶのはセンスあふれるデザイン、誰にも想像つかないような独創性、安藤忠雄や隈研吾のような建築家を思い浮かべてしまう方も少なくないのではないでしょうか。
マンションやアパート等の規格化された建物の図面作成・申請関係・監理を行う事務所もある。

建てたい建物の内容がほとんど固まっているけど、図面作成や申請関係・監理は自社では難しい、、、
そういった会社も多いから需要があるんだ!
私は学生のときに、設計事務所のイメージはデザイン性や独創性を追求するイメージだったため
設計事務所を避けていました。
マンションなどほとんど業務化された作業の中で図面を作成し確認申請等の申請関係を通しその建物を監理する業務について明確な認識があれば、設計事務所を選択肢の一つに入れていたと思います。
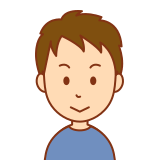
デザイン力にがないと設計事務所には入れないイメージだったけど、そんなこともないんですね!少しハードルが下がりました!
その他にも、申請関係のみを行う会社や図面作成のみを行う会社、設備設計・構造設計を主体で行う会社も多数あります。
戸建て住宅レベルでは図面を分けないことも多いのですが、マンションや事務所、店舗など大きな建物になるほど設備設計や構造設計は別で行うことが多いため専門性の高い仕事となることが特徴です。
*¹ 建築するためには確認申請はもちろんのこと他にも様々な手続きが地域によっても多数あります。
*² 工事が図面通りに行われているかを確認する業務。後に出てくる管理と混合しやすいため注意。

学校での設計課題はデザインがほとんどだったけど実際は、申請関係や法規を守りながら図面の作成・監理といった仕事が多いんだよね。
デザインについても敷地形状・周りの建物との関係性、法規があって色々な条件を経験しながら培っていけると思うよ!
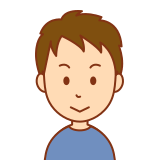
なるほど、、、
苦手意識を持っていたけどCADを触るのは好きだったし法規を守りながらの図面作成はゲームみたいで楽しそうですね!

むしろ若い頃から入っておけば、建築の知識がしっかりと定着しやすいし
たくさんの経験をした上で次の職場を選ぶのもいいかもしれないね!
さらに設計事務所の経験があれば独立も視野に入れられるよ!
ゼネコン
ゼネコンはすべてを行います。一言で言えば、総合建設業です。
えっ?と思った方も多いでしょうが、ゼネコンは設計から施工までトータルで請負ことができる会社が少なくありません。
だったら設計事務所は必要なくないかと思うわけですが、そうもいかないわけです。
今回は就職先の話のため簡潔に言うと、中学校くらいに習った三権分立です。
政治についてもそうですが、すべてを一つに任せるのはリスクが高いのです。
話しが脱線しました 笑
今回はゼネコンに就職した際に就くイメージが高いであろう現場監督について話をしていきましょう。
現場監督の仕事のメインは管理です。先程でてきた監理との違いに注意しましょう。
管理:現場を管理することです。工程・原価・品質・安全の4つの管理から成ります。
監理:設計図書のとおりに工事が行われているかを確認する。
実際工事を行うのはサブコンと呼ばれる各工事業者であり、それらの業者をまとめ上げるのが現場監督というわけです。

工事をするわけではなく、あくまでも現場が上手く回るように調整するのが現場監督の仕事というわけだね!
わたしはゼネコンに勤めたことはありませんが、友達や取引先の監督から聞く話によると「経験を活かして上手く調整できた達成感は最高」また、「これは俺が建てたんやぞ」と言えるような建物が増えていくのがやりがいだそうです。
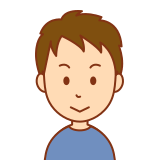
スポーツの監督みたいですね。確かに自分の采配で上手くできたときの喜びは高そう!
設計事務所を超えてブラックなイメージでしたが、2024年4月からついに建設業にも36協定の上限規制が適用され会社としても本気の対応を取らずにはいられなくなり社内改革が進んでいると聞いています。また、取引先のゼネコンでは女性監督もみることが多くイメージが変わってきていることが印象的です。
その他にも積算業務や建築を経験したうえでの仕事を取得する営業さんをやっている方も見えますので人が足りていない昨今の現状から現場監督以外の部署移動も考えられるバラエティに富んだ職種とも言えるかもしれません。

ブラックなイメージの強かったイメージのゼネコンだけど時代背景もあり、徐々にではあるけど環境が良くなりつつあると思うよ!
辞めてもらいたくないというのもあって待遇や教育についてもより良く・優しく対応していると聞いているよ。
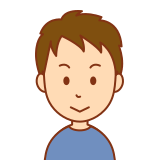
建築業界も残業について厳しく取締り始めているんですね!
(女性がいないのも懸念していたけど、いるのなら僕にも春が、、、、)

(なんか笑ってる、、、こわ)
ハウスメーカー
ハウスメーカーはおそらく一般の方々も一番馴染みのある職業ではないでしょうか。
展示場などに行って何社か家を見てもらいマイホームを建ててもらいました!
こういった人も多数いることでしょう。
つまり、一般の消費者と相対する業務が他の就職先に比べて多いです。
設計
設計は分譲住宅と注文住宅とで働く上で大きく違います。
| メリット | デメリット | |
| 分譲住宅 | ・接客ストレスが少ない ・棟数が多いため、早くたくさんの経験を得やすい ・決められた範囲内で自分の好きなように決められる | ・予算に幅がないため仕様は縛られやすい ・お客様との接点がない ・業務的になりやすい |
| 注文住宅 | ・お客様によって要望は違うため飽きにくい ・分譲に比べて頭数が少ないため集中できる ・グレードの高い商品を扱えたりする | ・お客様の時間に合わせる必要がある (夜の打ち合わせ、休日出勤) ・モンスターに当たるとストレスが半端ない |

お客様の理想の家を設計したいと思う人には注文住宅の設計がおすすめだね!
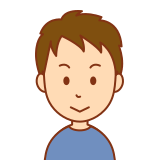
接客は苦手だけど家の設計をやりたいという人は分譲住宅の設計の選択肢があるんだね!
私がハウスメーカーに入った当初はこの注文住宅の設計に憧れて入りました。
お客様の夢のマイホームを実現する素晴らしい仕事だと思います。
ここで注意しておきたいのは、注文住宅でもお客様との打ち合わせに営業のみが出席し設計が出ないといった会社もあります。その場合、お客様の要望も営業からの又聞きとなるため、相対していても難しい要望の反映が更に難しくなりますので、しっかり調べておくと良いと思います。
いざお客様に合うと営業からの聞いていたことと全く違う意見が出てきたびっくりした事があると同僚から聞きました。
施工監督
施工監督については、ゼネコンで説明した業務と大差はないのですが規模が違うためハウスメーカーの場合現場を複数もつことが印象的です。また、各職人との距離も近いです。
ゼネコンの場合、サブコンから番頭が一人ないし二人代表で現場監督から指示を受け、職人たちへ指示する事が多いのですが、ハウスメーカーの現場監督の場合は各工事の職人へ直接指示することの方が多いです。
住宅は工期が比較的短いため、現場で組む方々と相性が悪くてもすぐに代わるといった利点もあると思います。
私は上棟や引渡し時などにお客様の喜ぶ姿をみてやりがいを感じました。

お客様と直接話す機会が多い分、お客様の喜んでる姿が直接見れたり、感謝されるのは本当にやりがいがあるよね!
せっかくならお客様と一緒に作り上げることができる会社がおすすめだね。
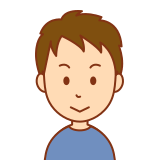
お客様の夢のマイホームを実現する仕事、、、考えるだけでかっこいいですね!
デベロッパー・不動産会社
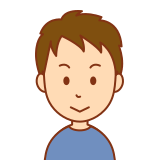
デベロッパー・不動産会社?、、、技術職の建築学生が行くところではない気がします。
もちろん投資用マンションや土地活用アパート、冷凍倉庫等がありますがそのほとんどは設計事務所に図面作成監理を依頼し、ゼネコンへ施工管理を依頼します。
ではどこに必要なのか。次の二点になります。
- 開発・ルール(決まり)の作成
- ルール通りに設計事務所・ゼネコンが仕事しているかの確認
自社のブランドとしてマンションを売り出すとしてそれを商品化するために仕様を決めていくわけですがそこにはある程度の知識が必要となります。
全くの素人では厳しいため社内的に建築学生の採用や建築知識のあるものを中途採用し、一定人数へ継承し育てていると言うことです。

商品化するためには、やはり専門的な目線が必須というわけだね!
2.について
設計事務所の監理のメインは図面通りになっているかを確認しますが、一番は建築基準法やその他省エネ法などの法規をメインに確認します。違反が一番怖いですからね。つまり、依頼会社のブランドを守れているかまで確認できているかは怪しいところです。
もし、法規上には関係ない不備があった場合もちろんゼネコンは不慮があれば対応してくれる場合がほとんどでしょう。
しかし、一度世に出てしまえば情報は拡散します。例えば
- なんかベランダに変な段差があるだけど、、、、
- 〇〇会社のマンションで水漏れあったらしい、、、、
- 新築のはずなのに、床傷だらけなんですが、、、、
ネットの書き込みがあった際、施工したのはゼネコンでも販売元のデベロッパー・不動産会社の信用に傷がつくのです。
ある程度の知識を持ち、設計、現場監督と打ち合わせを行い、確認する。このような人材が必要というわけですね。

建築と不動産は切っても切り離せない関係だということがわかったね!
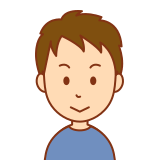
不動産業界、、、全然見てもいなかったけど選択肢に入れてみたいと思いました!
まとめ
今回は、建築学生のメインとなる就職先についてまとめさせていただきました!
もちろん他にもありますが専門性が強い設備関係やプラント等のため紹介しておりません。
今回の記事を見て、えっそうなの?意外と向いてるかもな!そう思っていただける情報を載せられたのなら幸いです。
就職活動中には、盲目になってしまうことも少なくありません。設計しかないと思っていても施工監督が向いていたり、デベロッパー・不動産会社なんてありえないと思っていても実は楽しかったりと視野を拡げることで選択肢も増えるのではないでしょうか。
現代は転職時代!一度失敗しても二度三度の転職は全然問題視されません。
どこも人が足りてないので、、、、
その中で是非、建築・不動産を選んだ方にあった就職先を見つけていただけたらと思います。
私はまだまだ未熟ですが、建築・不動産業界をもっと盛り上げていけるように興味を持ってもらえるような情報を発信していきますのでぜひ次回も読みに来てくださると幸いです。

それでは皆さん、またね~!
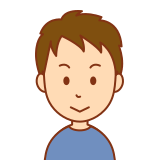
ありがとうございました〜!


コメント